
生産量は世界の綿の生産量の5%と希少な原綿『ピマコットン』を使用した布団カバーです。ピマコットンは綿の中でもトップクラスの繊維長で、『綿のカシミヤ』とも称されます。
そんな最高級の綿を使って、織物の町、山梨県富士吉田市の職人が織り上げた生地となります。
本製品の特徴 商品一覧 ピマコットンについて ジャガード織りについて ふじやま織りとは? 織りの工程 絹織物の産地として栄えた富士吉田市|郡内織物
細番手の糸で高密度に織ることでシルクのような柔らかでしなやかな肌触りを実現しています。使う方に良質で贅沢な睡眠をご提供できます。
高級旅館やラグジュアリーホテル、リゾート施設、エグゼクティブルームなどで採用されている生地となります。製造元から直に仕入れての販売形態のため、リーズナブルな価格でのご提供となります。
■ 組成:ポリエステル70% コットン30%
■ 生地幅:160cm(シングルサイズ)
■ 織り:ふじやま織

この掛け布団カバーの特徴は?
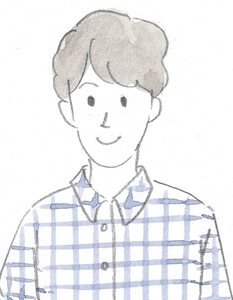
ふじやま織の特徴は『ジャガード織り』です。糸の種類で模様や色彩を浮き出す織り方です。高級綿ピマコットンを使って、機織りのそれぞれの工程に特化した専門工場が連携して布団掛けカバーの生地を織り上げています
富士吉田の織物の特徴は、ジャガード織りであることです。
ジャガード織りとは、模様・柄を、あらかじめセットしておいた異なる色や種類の糸で織って織り方です。後染めではないため、生糸本来の良さを最大限活かすことができ、繊細な肌触りと高い耐久性を実現できます。その分、ジャガード織りは各工程に高い技術が求められ、それぞれに職人性が求められ、工場の連携が要(かなめ)となります。
本製品は、株式会社山七さんが設計、企画、デザイン、検反を行い、染めや整経、機織りなどの工程を地場の工場が連携して織り上げた生地となっています。

ピマコットン(ピマ綿)は、世界で生産されているコットンの中でもトップクラスの繊維長を持つ素材で、超高級コットンとして知られているものの一つです。世界三大コットンである、ギザ綿、新疆綿(しんきょうめん)と並び、最高級の製品を作るための素材として選ばれています。

ピマとはコットンの品種のことを言っており、エジプト綿とアメリカ綿との異種交配によって作られたもののことで、アリゾナ州のピーマ群に産地の由来があるため、これをピマコットンと呼んでいます。ピマコットンは、「綿のカシミヤ」と呼ばれ、カシミヤのような風合い、シルクのような光沢、なめらかな肌触り、そして耐久性に優れた素材です。世界で生産されているコットンのうちたった5%しか取れない、大変希少価値の高いものです。
世界三大コットンと呼ばれるものは、3つの産地で生産されています。ピマコットンはアメリカの南西部やペルーで、ギザ綿はエジプトで、そして新疆綿は中国の新疆ウイグル自治区で栽培されている超長繊維綿のことを指しています。
超長繊維綿は、一般的な綿繊維に比べて長さが違います。綿繊維の一本一本の長さは3〜4cm程度あり、一般的な綿繊維の2〜3倍あるため、細く、しなやかで丈夫な糸を作ることができるのはこのためです。
綿繊維は、繊維長が長くなればなるほどランクが上がります。超長綿は35mm以上、長繊維綿は28mm以上、中繊維綿は21〜28mm程度、さらに短繊維綿は21mm以下と分類されています。
綿素材の超長綿を使った糸は大量に手に入るものではありません。従って、繊維長が最も長い高性能な素材を使った糸は必然的に価値が高くなり、この糸を使った布地は必然的に高品質な材料となり、付加価値の高い商品へと生まれ変わるのです。
繊維長の違いによって糸の品質は大きく変わります。糸は繊維を一定の方向に揃え、必要とする細さに引き伸ばしたのち、撚りをかけて作ります。この長繊維を使った糸は、繊維の一本一本が長いために、細く、ほどけにくく、強度の強いものとして仕上がります。このような糸で作った布地は、毛羽立ちがなく、しなやかで光沢があり、軽くて薄い、そしてしっかりとした肌触りのよい製品となり、高級製品の品質を保証するための材料となっているのです。
長繊維の素材は他にもありますが、長繊維であれば何でも良いという訳でもありません。一般的に、長繊維に該当するものは化学繊維とシルクであり、コットンは実は短繊維として分類されているものです。その短繊維であるコットンのうち、大変貴重な超長繊維綿に該当するものだけを選び抜き、高品質な綿生地の素材を作っているものの一つが、まさにピマコットンなのです。
ピマコットンは、肌触りや吸湿性に優れており、普通のコットンを使った素材とは明らかに違いがあります。ラルフローレンやアルマーニなどの世界の高級ブランドが使う布地としても、永く愛され選ばれている素材です。
「ふじやま織」は富士吉田織物協同組合によるオリジナルブランドです。この掛け布団カバーも、古くから郡内織物として知られる富士吉田の機織りの技術を活かして、伝統の細番手、高密度ジャガード織りで、地域の職人たちが織り上げる最高品です。
甲斐絹の時代から培われた洗練された技術と地場の工場で連携する小回りのきく生産体制が強みで、その先のご提供先の人びとのニーズに柔軟に応えます。
本製品は、設計、企画、デザインを株式会社山七さんが、撚糸(ねんし)、綛上げ(かせあげ)、染め(染色)、整経などは富士吉田で古くから操業を続ける地元の会社や職人さんたちが行っています。

| ❶企画デザイン | 織物の柄や色、糸の太さや素材、撚数などを決めます。 |
|---|---|
| ❷紋意匠を作成 | デザインどおりの柄を描くために、紋意匠という紋紙ないし電子データを作成します。ジャガード織りでは、この意匠図がたて糸とよこ糸を制御し、生地に模様を描いていきます。 |
| ❸撚糸(ねんし)、 綛上げ(かせあげ)、 染め(染色) |
原糸に撚り(より)をかけて強度を出す『撚糸(ねんし)』、ボビンから綛(かせ)に巻きなおす『綛上げ(かせあげ)』、そのあとの『染色』を行います。 |
| ❹整経、 撚り付け |
染められた糸を、必要な密度や本数、長さにして巻き取る『整経』、糸を均等な張力で一本ずつ繋ぐ『撚り付け』を行います。 |
| ❺織り、機織り(はたおり) | 糸を織り生地にする『機織り(はたおり)』を行います。ここでジャガード織りを行い、企画デザインで作成したいた繊細な模様がここではじめて現れます。 |
| ❻検反 | 織り上げた生地に傷や汚れが無いか検査する『検反』を行います。ピンセットや針などを使って、職人が細かくチェックします。 |

月のかつらの 桂川
ひびく 杼(ひ)の音 筬(おさ)の音
——富士吉田市立明見小学校 校歌より
地元の小学校の校歌にも歌われるほど、機織りの音は富士吉田の人々の暮らしに身近でした。杼(ひ)は、よこ糸を通すためにシャトルのように滑らせる道具で、杼で打ち込まれたよこ糸を押さえて織り目の密度を決めるのが筬(おさ)という道具です。トントン、カラン。
桂川は富士山から流れる清涼な川で、『吉田で染め出す色は他では出せない』と言われていたそうです。

富士山の北麓にある富士吉田市(ふじよしだし)と西桂町(にしかつらちょう)を中心とした地域は、古くから『郡内織物』『甲斐絹』として知られ、主に絹織物の産地として栄えました。その歴史は1,000年以上前に遡ることができると言います。
1)富士伏流水というほどよいミネラルを含む清涼な水に恵まれていたこと
2)甲府や都留など近くに養蚕産地があったこと
そんな地の利が織物産地の技を研鑽させました。時代は移り、現在は多品種の糸を使って高密度のジャガード織りを行うようになります。といっても、地場の工場が連携して一つの織物を仕上げる形は今も変わらず、寝具や衣服、カーテン、ネクタイなど織りに関わるニーズに幅広く応える機織りの町となりました。







