-
category
-
tukurite
�����ʡ�����̵����
��ZABUTON�ץ�����ϡ���ʪ�Τޤ����������ٻε��ĻԤˤƳƹ����ο��ͤ�Ϣ�Ȥ��ƿ���夲���ʼ��ι⤤���ʤǤ���
���ܤ�����Ūʸ���������������ƥ����ȤΥǥ�����ϡ������ҤΤ�������Ū�ʤ������ˤ�����ƥꥢ��ʷ�ϵ��Τ������ˤ��Ϥ����ߤޤ�����ӥ��Ҵ֡����ܴ֡�������ߤεҼ��������餷�ʤɡ�����Υǥ�����ġ���Ȥ��Ƥ��Ȥ�����������
��ʪ�Τޤ����ٻε��Ĥˤơ����ͤ�ο��ͤȤ����Ĥ�ι��줬�������Ȥ�Ϣ�Ȥ��ƿ���夲��������κ٤�����ʪ���Ϥ�ȩ����Ҥ���ǽ����������
�ܼ�
����
�ʲ��Τ����줫���餪���Ӥ��������ޤ���
���������ĥ��С��Τߡ���錄�ʤ���
���������ġ��������괰���ʡ�
�����ƾ��ʥڡ����ˤơإ����Ȥ������٥ܥ���ξ�ˤƤ����Ӥ���������
�ʼ�
¦�ϡ��ݥꥨ���ƥ�95% ��5%�ʰ���Ǥ������ʤˤ��ۤʤ�ޤ���
������������㥬���ɿ���ʤդ������
��錄����90% �ݥꥨ���ƥ�10%
������
55��59cm������Ƚ�ʤᤤ����Ф�ˡʤ�����M��������
59��63cm��ȬüȽ�ʤϤä���Ф�ˡʤ�����L��������
50��50cm����������
�����ʤˤ�ä����٤륵�������ۤʤ�ޤ���
������
���ܡ�¦�ϡ����ܡ�
������˥�������ܡ�
����
���ʡ�����̵��
�����������졢�̳�ƻ��Υ������

�ٻε��ĤϿ�ʪ����ˤ�Ĺ���ơ��������Ϥ��������Ƥ���ä�ʹ����
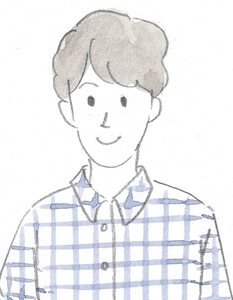
�������ٻε��ĻԤϸŤ����鵡���꤬³�����Ƥ���Į���ٻε��Ĥο�ʪ����ħ�ϡ���μ�����������ͤ俧�̤��⤭�Ф��إ��㥬���ɿ���١����줾��ι������ò��������繩�줬�����ʣ�����äơ�Ϣ�Ȥ��ư�Ĥ����Ϥ�夲�Ƥ�Τ�������

��η뾽�ߤ���
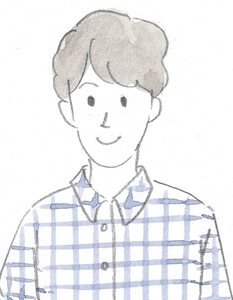
���Ѥη뾽�äƤ��ȡ�

���������λ��Ϥο���������ħ�ϡ�
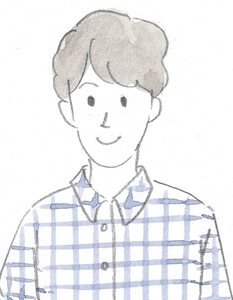
�ʤ�Ȥ��äƤ⡢�����ᡣ�����顢���ͤ俧�����䤫��ɽ���Ǥ����

�ʤ�������������䤫�ˤʤ�Ρ�
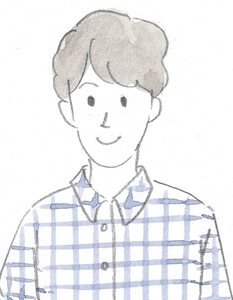
������Ȱ�äơ���������ο��λ��Ȥ��뤫�顣������Ǥϡ�2�����Ĥޤꤿ�ƻ�Ȥ褳��������롣�Ǥ�������Ϥɤ�ʿ��Ǥⲿ���Ǥ�Ȥ��롣���줬������㥬���ɿ���������ǡ��ٻε��Ĥδ���Ū�ʿ������ʤ��

����äƴ��פߤ���
�֤դ�����פϡ��ٻε��Ŀ�ʪ��Ʊ�ȹ�ˤ�뿥ʪ���ʤΥ��ꥸ�ʥ�֥��ɤǤ���
���ʪ�Ȥ����Τ��뻳�����ٻε��ĻԤ��濴�ˡ����͡����ꤿ����Ϣ�ȡ����Ϥˤ�äƿ���夲����ǹ��ʤȤʤ�ޤ���
��ʪ���ϤȤ����ݤ�줿�����������ᵻ�ѡ����ּꡢ��̩�٤�¸�������̩�ʥ��㥬���ɿ��꤬��ħ�Ǥ���
�ֻ����ˤ��뵡����Τޤ��פ����������ܾ��ʤҤ������������

�¤���˵Ӥ䤪���β����ߤ����ĤΤ��Ȥǡ��¤꿴�Ϥ��ɤ������ꡢ�β���å���ʤ��褦�ˤ���������ä���ΤǤ��������Ĥȸ��äƤ��ޤ������¤����ĤǤϤʤ�����ͳ�褷�Ƥ��ޤ�������䧡ʤष���ˤ�Ťͤ���Τǡ������¶�Ȥ��ơ���ʬ�ι⤵�丢�Ҥξ�ħ�Ȥ��ƻȤ��Ƥ�����ΤǤ���
���Τ����¶�Ȥ��ƻȤ��Ƥ�����Τϡ����衡ʤ��Ȥ͡ˤؤ��Ѳ��������ߤκ����ĤȤ�����ڤ������Ѥ����褦�ˤʤäƤ��ޤ�����
�����Ĥϡ������礭���ˤ�äƼ�ˣ��Ĥμ����ʬ�व��Ƥ��ޤ����¤��������ʤΤϤ��Τ��������ष���ʤ�������ʳ��Ϥ��٤�Ĺ�����Ȥ�¸���Ǥ�������
43cm��47cm��ʪ������Ƚ�ʤ��㤻���Ф�ˡ�43〜50cm����������ʪ�����ġʤ����֤Ȥ�ˡ�51cm��55cm��ʪ������Ƚ�ʤ���Ф�ˡ�55cm��59cm��ʪ������Ƚ�ʤᤤ����Ф�ˡ�59cm��63cm��ʪ��ȬüȽ�ʤϤä���Ф�ˡ�63cm��68cm��ʪ���˻�Ƚ�ʤɤФ�ˡ������67cm��72cm��ʪ������Ƚ�ʤᤪ�ȤФ�ˤȸ��äƤ��ޤ���
����Ū�ˤϡ�����Ƚ��ȬüȽ��������ڤ��Ƥ��ޤ���
| �����Ĥ�̾�����Ƥ��� | �������ʽġ߲��� |
|---|---|
| ����Ƚ�ʤ��㤻���Ф�� | 43cm��47cm |
| �������ġʤ����֤Ȥ�� | 50cm��50cm�ʤɡ�43��43cm��45��45cm�ʤɤ⤢��ޤ��� |
| ����Ƚ�ʤ���Ф�� | 51cm��55cm |
| ����Ƚ�ʤᤤ����Ф�� | 55cm��59cm |
| �˻�Ƚ�ʤɤФ�� | 63cm��68cm |
| ����Ƚ�ʤᤪ�ȤФ�� | 67cm��72cm |
���ܤ����������Ĥ���ˤϡ��Ť����һ���ˤޤ��̤�ޤ��������Ĥϡ��������侲�˺¤�Ȥ��˵Ӥβ��ˤ��Ƥ��äƺ��꿴�Ϥ��ɤ����뤿��Τ�Τǡ�����ɤ���Ƥʤ��Ȥ�����̣��������Ƥ��ޤ���
���θ��ϼԤ���Τʤɤ����Ϥξ�ħ�Ȥ��ƻ��Ѥ����аޤ����ꡢ���ߤΤ褦������ʤ������褦�ˤʤä��ΤϹ��ͻ��������ʹߡ����̤���ڤ���褦�ˤʤä��Τ�������������äƤ���ǡ��������Ѥ����Ϥ��̻������褦�ˤʤä��ΤϾ��¤λ���ˤʤäƤ���Ǥ��������ƶ�ǯ�Ǥϡ����å���Фκ����Ĥ����䤵���褦�ˤʤꡢ�������Ӥ������礭���Ѳ����������ʤ��ǽ�������¤Υ����ƥ�ȤʤäƤ��ޤ���
���Ҳ𤹤��ZABUTON�פϡ�������Ѳ����б������͡��ߥȵ�ǽ����Ū�Ȥ��Ƴ�ȯ���줿��Τǡ����ʼ������Ϥ������Ϥ줾������Ӥ��б���������ΤǤ�������κ����ĤȤ��Ƥλ��ѤϤ������Τ��ȡ����å����䥤��ƥꥢ�Ȥ��Ƽ�ͳ�ˤ��Ȥ������������ΤȤʤäƤ��ޤ�������Ƚ��ȬüȽ�������50cm���Ѥ�3�����������Ƥ��ޤ���
�����ĤȤ��Ƥ��Ȥ��ˤʤꤿ�����ˤ�����Ƚ��ȬüȽ���å����Ȥ��Ƥ��Ȥ��ˤʤꤿ�����ˤ�50cm���Ѥ����Ӥ���������Ф���������Ȼפ��ޤ���
�����Ĥϡ��¤꿴�Ϥ��ɤ����뤿���ƻ��Ȥ��ơ�������ʤɤ˺¤���˵Ӥ䤪���β��ˤ��Ƥ��äƻȤ��ޤ���������Ф��ơ����å����ϡ����ե����ʤɤǤ��Ĥ������δ˾�Ȥ��ơ������֤������������ˤ��Ƥ��äƻȤ��ޤ���
����Ū�ˤϡ������Ĥ���٤�ȥ��å������������餫�������������⤤��ΤȤ��ƺ���Ƥ��뤳�Ȥ�¿���Ȼפ��ޤ������������ߤǤϡ������Ĥ⥯�å��������Ū��ͳ�����Ӥ����Ѥ����褦�ˤʤäƤ��ޤ�������ޤ�ˤ������ˤ����ꡢ���������ĤȤ������Ѥ����ꡢ�ػҤξ����ʪ�Ȥ��ƻȤä��ꡢ�ʪ����Ȥ��뤿����ɶ�Ȥ��ƻȤä��ꡢ�ޤ��ϥ���ƥꥢ�ΰ����Ȥ������Ѥ���뤳�Ȥ⤢��ޤ���
���Τ褦�ˡ����Ӥ����Ϥ��ʤ깭���ʤäƤ��ꡢ��ǽ��ǥ������Ż뤷����ͳ��ȯ�ۤ���ǻȤ��륢���ƥ�ΤҤȤĤȤʤäƤ��ޤ���
�ٻε��Ĥο�ʪ�κ������ħ�ϡ����㥬���ɿ���Ǥ������㥬���ɿ���ϡָ�����פǤϤʤ���������ס����ޤ��ޤʿ�������ۤʤ��餫�����Ѱդ����վ��ޤˤ��л�Ȱ�θˤ�ä����Ͼ�������̤�����ͤ������Ƥ����ޤ����վ��ޤκ��������ᡢ���С�����ʤɡ��٤���ʬ����줿������Ĥ��Ĥ˿��ͤˤ���Ȥ�����졢���Ѥε�������ͭ���뤤���Ĥ��ι��줬Ϣ�Ȥ��ư�Ĥο����¸����ޤ������Τ��ᡢ�ޤ����Ͼ�ε��Ѥη뾽�ȸ����ޤ���
�����ʤϡ��߷ס���衢�ǥ�����������һ�������Dz��ʤͤˡ�幾夲�ʤ��������ˡ�����������ˡ����Фʤɤ��ٻε��ĤǸŤ�������Ȥ�³�����ϸ��β�Ҥ俦�ͤ������ԤäƤ��ޤ���
�����ٻε��ĤǤο������ħ�����ҤΤȤ��ꥸ�㥬���ɿ���Ǥ��������ּ����ɮ���٤���ħ�ΤҤȤĤǤ����Ǥ�٤���硢ȱ���Ӥ�1/3�����褽20�ǥˡ���κ��ּ�θ���ݥꥨ���ƥ�ǿ���夲�ޤ������Τ��ᡢ����٤���ȩ���꤬�ɤ����ϤȤʤ�ޤ������ʪ�����帨����ˤ��ݤä��⤤���ѡ��٤䤫���б��Ǥ����ͤΥˡ����˱������������������Ϥȿ�ʪ���̤��ơ�������οͤξд���¤��ޤ���
�ߥͥ��˭�٤��ٻλ�ϼ��ͯ��������ᤷ���ۤʤ뿧�λ�����䤫�ʿ��̤�����夲�ޤ���
�Ǥ�٤���硢��20�ǥˡ��롢���ʤ��ȱ���Ӥ�1/3�ۤɤνŤ������ʤ����ּ�λ�Ǻ٤䤫�����Ϥ���夲�ޤ���
���Τ褦�ʶ˺٤λ�ǿ���夲�Ƽ¸������ֹ�̩�١פ����Ϥ��������Ĥ仱�����ϡ������ƥͥ������ʤ���̩�����ѵ����������뿥ʪ�Υˡ����˱����ޤ���
1,000ǯ�ʾ������̤뤳�Ȥ��Ǥ���ȸ�����ط��ʪ�١����ͻ���˹����Τ�줿�ع��帨�١��������Ϥ�Ĺ�����֤����ݤ�줿�⤤���ѡ�������Ѳ��˹�碌�ƾ������줿�����Τ������������Ϥ��줫����Ͼ�λ��ȤȤ��Ƽ����Ѥ���ޤ������Ϥȿ�ʪ�����������¿�ͤʾ��ʤ��̤��ơ�������οͤξд���¤��ޤ���
��ʪ�ε��פϴ��ס����줾��ι�����Ĺǯ�ο��ͤ��������������ޤ���
| ❶���ǥ����� | ���ǥ�����ι����Ǥϡ���ʪ�ο����������ΤϤ������Τ��ȡ����Ӥˤ�뵡ǽ�����礤��ǥ�����ˤĤ��Ƥ��ޤ��ޤʻ��ͤ���ꤷ�Ƥ����ޤ�������ˡ�����Ǻ��������Dz���ʤ�ꤹ���ˡ���ʪ��̩�٤俥�����ʤɤˤĤ��Ƥ�٤������ꤷ�Ƥ����ޤ��� |
|---|---|
| ❷��վ��κ��� | ��վ��ϡ��ްƤ�ʪ�Ȥ���ɽ�����뤿��ˡ��л�Ȱ���Ȥ߹�碌��ͤ��ưվ��ޤˤޤȤ�빩���Ǥ������������վ��ޤϡ���վ������ˤ��Żҥǡ������Ѵ�����ƿ����������ޤ������㥬���ɿ���Ǥϡ����ΰվ��ޤ����ȤʤäƷл�Ȱ�θˤ�ä����Ͼ�����ͤ������Ƥ����ޤ��� |
| ❸Dz��ʤͤˡ� ��幾夲�ʤ��������ˡ� ������������� |
��ʪ�θ��Ȥʤ븶��ˡ�Dz��ʤ��ˤ���ɬ�פʶ��٤�Ф�������Dz��ʤͤˤȸ����ޤ���Dz��ʤͤˤ�����ä���ϥܥӥ�˴�����Ƥ��뤿�ᡢ�����������˥ܥӥ�幡ʤ����ˤ˴����ʤ������������ꡢ�����幾夲�ʤ��������ˤȸ����ޤ������θ�����������ǡ�Ʊ������Ƹ������꿧������ʤ�����κ�Ȥ�Ф�������������ޤ��� |
| ❹���С� ��Dz���դ� |
�����ᤵ�줿�����줿�ܿ���̩�١�Ĺ���ˤ������ä��¤١����ޤ��˴�����빩�������Фȸ����ޤ����ޤ��������˥��åȤ��줿���ޤ��ϡ���������Τ˸���ݤ˿������Ƥλ�Ʊ�Τ��ӤĤ��ʤ���Фʤ�ޤ����ܤ��Ĥλ�������ĥ�ϤǷҤ����٤ʹ�����Dz���դ��ȸ����ޤ��� |
| ❺�����ʤ������礯�ˡ����� | 1���ܤΥ��ƻ�Ͽ��ͤˤ��1〜2���֤����ƿ����˥��åȤ���ޤ���������Ϥˤ��뤿��ι���������������ȸ����ޤ���������Ȥ����л�˰�����Ǥ�����ȤǤ������åȤ��줿�л��岼��ʬ���Ƴ������������δ֤˰���̤����Ȥˤ�����Ϥ�����Ƥ����ޤ������㥬���ɿ����ȿ��ͤε������٤�ʣ�������ꤢ���뤳�Ȥ���ǽ�ˤʤ�ޤ��� |
| ❻��ȿ | �ž夬�ä����Ϥ˱�������̵������Ĵ�٤빩����ȿ�ȸ����ޤ����ܻ�ˤ�뿦�ͤ���ǫ�ʺ�Ȥ��ʼ����äƤ��ޤ���ɽ����ǫ�˳�ǧ�����ԥåȡ��ˡ��ϥ��ߤʤɤ�Ȥäơ�������Ȥ�Ԥ����Ȥ⤢��ޤ��� |
��衦��¤���γ�����һ�������ˡ����ʤؤ��ۤ���ʹ�����ޤ�����
�ʳ�����һ�������ɽ������ ����ů�𤵤� ����


�ٻλ���ϼ�˰��֤����ٻε��Ļԡʤդ��褷�����ˤ�����Į�ʤˤ����Ĥ���礦�ˤ��濴�Ȥ����ϰ�ϡ���Ȥ�ȸ���ʪ������Ǥ�����
�ط��ʪ�٤Ȥ��ƸŤ������Τ�졢������ˤ�1,000ǯ�ʾ������̤뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ������ͻ���ˤϹ��帨�Ȥ��ƹ����Τ��ޤ�����
����ʡ�����٤��Ǥ��븨��ʪ�λ��ϤȤ��ƹ���̾���������Τϡ��ٻ���ή��˷äޤ�Ƥ������ᡢ�����ƶ����ϰ���ٻε��ġ���α�����ܤʤɡˤ��ܻ��Ȥ�����Ǥ��ä�����Ǥ�����
������Ѳ��˹�碌�ơ�����˥��㥬���ɿ����Ԥ��褦�ˤʤꡢ�������٤��Ͼ�ι���Ʊ�Τǹ��礤�����ߤϡ��ݥꥨ���ƥ�ο����������ơ������Ĥ俲�����������ʤ�����������Υˡ�������ָ��Υ桼�����б�����褦�ˤʤ�ޤ�����
�ؿ���٤ˤĤ���ΤΡ�����١��͵����̤����䤨�뤳�ȤΤʤ��ٻλ�����ή������ᤢ��������ο���¾�ǤϽФ��ʤ��ȸ���줿�����Ǥ���

���ܤˤϿ�ʪ�λ��Ϥ������Ĥ�����ޤ������ɤ�⤳��⡢��������Ū�����丶�������������ϩ��ʸ����ؤ��ʤ��顢����Ω���ޤ�����

���ʤ��ٻε��ġʤդ�����ˡ������ʶ������ˡ����ԡ�ð�Ȥ��������ؿ���ˡ����ʷ���ݡˤʤɎ�����
�ʤʤ���ʷ���ݡˡ��;��ʱ����ʡˤʤɎ�����
�Ӥʤ�������������ʪ�ˤʤɎ�����
�㿥ʪ���ʿ�ʪ������ʪ���ӿ�ʪ��Ʊ������Ǥ⡢����Υˡ����˹�碌�ơ������������Ϥǿ�����������ƺ��ˤĤʤ��ޤ�����
��������Ϥε����Ȥ�����������ε���������ΰ����˼������ƤߤƤϤ������Ǥ��礦����







